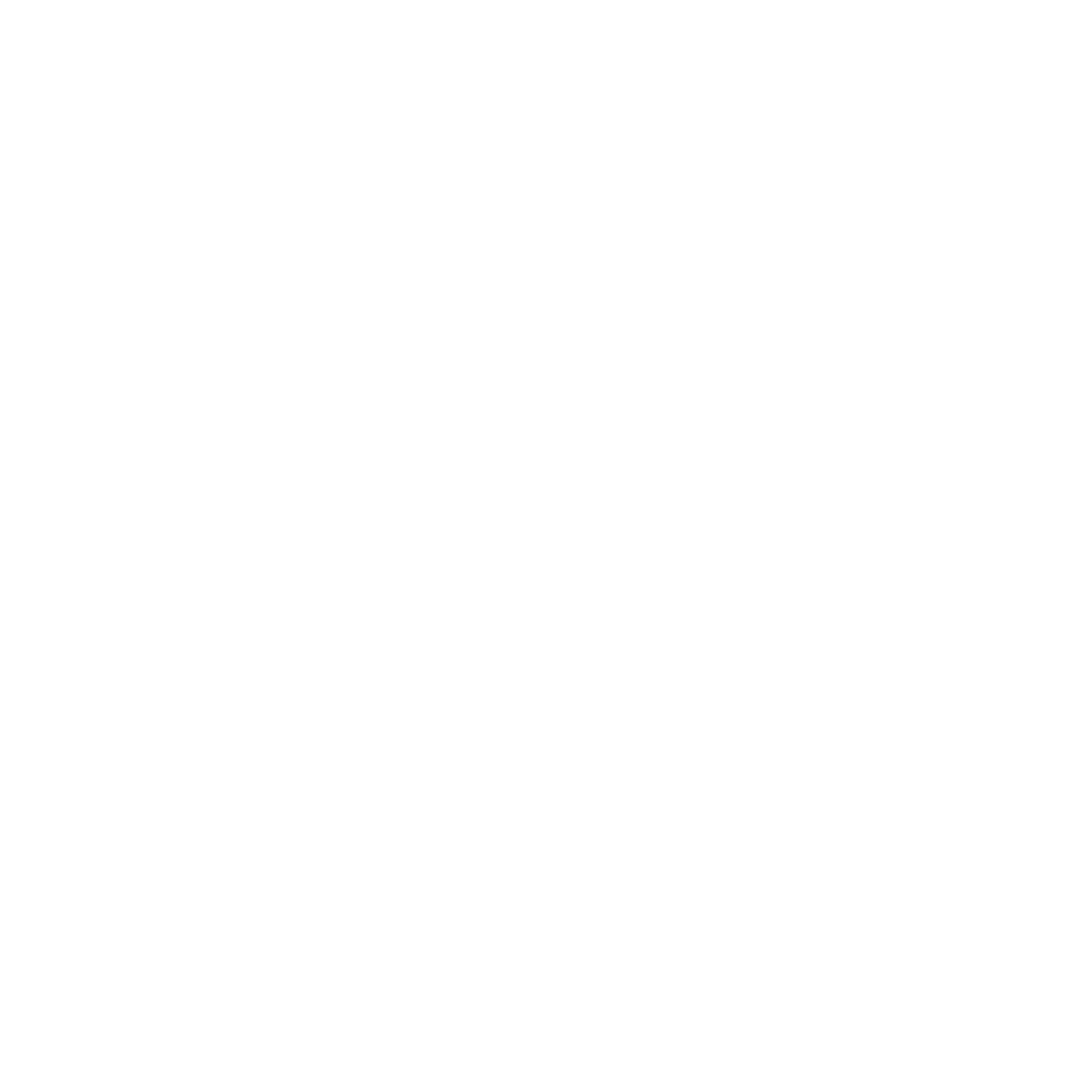1億円プロデューサー
社会の実現
プロデュースシンキング®︎
(プロデュース思考®︎)の
実践・教育・研究・啓発を通じて、
プロジェクト型社会において
個の想いとあり方を起点に
新たな価値を創造・発信できる人と
機会を創出し
1億総プロデューサー社会の
実現を目指します
PRODUCE THINKING LAB 設立背景
これまで組織を中心に事業は創造されてきましたが、今では個が個と繋がることで生まれたプロジェクトから新たな価値が創造される時代になってきました。つまりオペレーション型経済活動からプロジェクト型経済活動にシフトしています。
プロジェクトが中心となった事業開発の現場において、プロジェクトを発起する前から寄り添い、発起後も推進していくことができるプロデューサーの存在が大きく必要とされています。
PRODUCE THINKING LABでは、プロデュースの事象を集め、 プロデューサーの生態系を研究し、教育・啓発・実践に活かすることで、世の中にある幾多のプロジェクトに対して、プロデューサーの存在が成果に導いていくことを目指しており、これまで語り継がれたり、見て真似してきた暗黙知を形式知に、個人知を組織知に昇華していくプロセスをつくってまいります。
PRODUCE THINKING LABでは、プロデュースシンキング®︎(プロデュース思考®︎)に基づく教育プログラムの体系化、実践機会の創出、研究活動の発信、イベントや記事を通じた啓発活動を積極的に行い、全ての人がプロデュースシンキング®︎(プロデュース思考®︎)を獲得できる社会を創出してまいります。
- 「プロデュースシンキング」「プロデュース思考」は設立発起人である株式会社ネームレスが商標を取得しています。
取り組みのアプローチ
活動内容
-
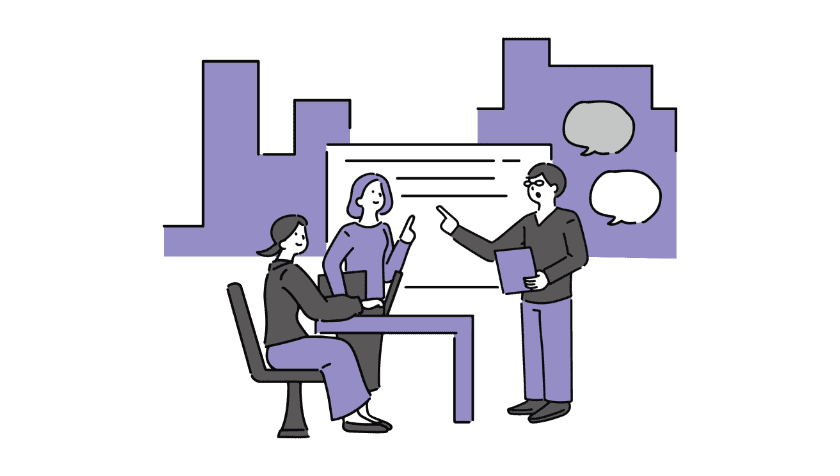
法人向け研修企画・実施
企業の事業開発部門への研修として導入をしていただいています。能力要件定義から研修プログラムの設計、各講座のファシリテーションや運営までワンストップで実施させていただきます。
-
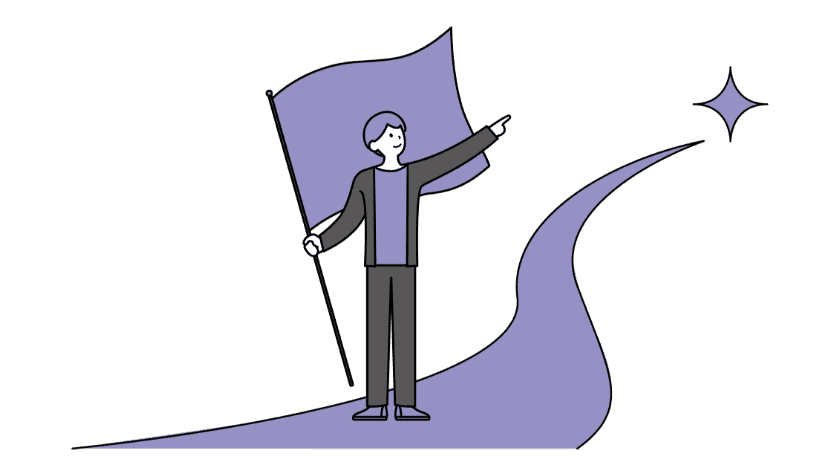
法人研究会員と自社プロデュース研究
企業から研究員を選出していただき、自社をプロデュースするという大枠のテーマのもと、研究テーマを決めて共にプロデュースシナリオを描くまでの研究活動をしています。
-
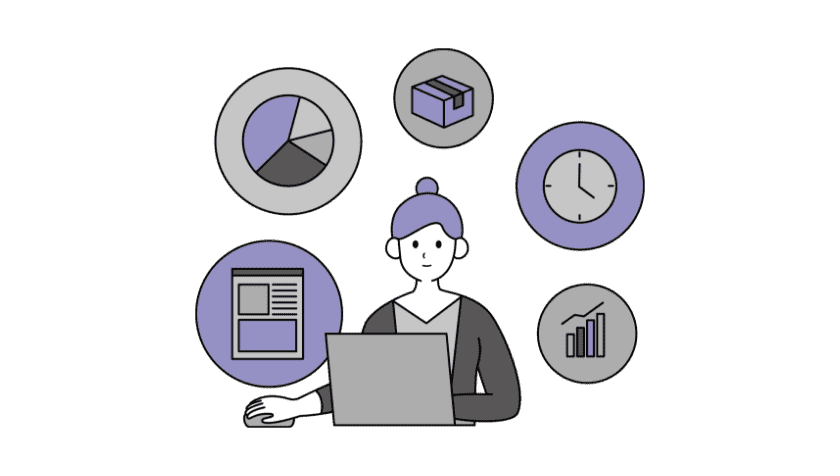
プロデューサー育成プログラムの開発
協業形式で特定の領域やテーマに対して、プロデュースシンキング®︎(プロデュース思考®︎)メソッドを軸としたプロデューサー育成プログラムを設計開発し実施しています。
-
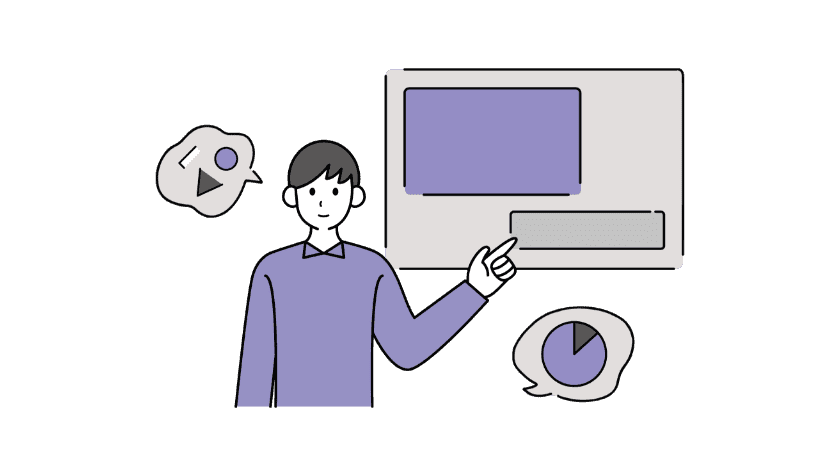
会社公認 企業内ゼミ
自社をプロデュースするという研究活動の延長で、研究員が自社内でラーニングコミュニティとしてのゼミを立ち上げ、参加者の取り組みを共有し、学び合いながらブラッシュアップする機会を創出しています。
研究・活動内容
実践
様々な新規プロジェクトに伴走しプロデュース活動を実践してまいります。ビジョニング、チームビルディング、顧客策定、PoC、PMF、ビジネスモデルの構築など、ワンストップで事業開発をプロジェクトチームの一員として共に推進してまいります。あくまで実践を通じての事業開発をしていくことが最重要であると考えているため、企業・自治体・大学・個人間など様々なバックグラウンドを持つプロジェクトに適応できるようにしております。
研究
プロデュースシンキングの体系化に向けて、日々プロデュース事例を調査し、言語化・モデル化しております。
成功事例・失敗事例はもちろん、実践を通じて得られた結果と過程を、人、組織、事業内容、時期などあらゆる側面から科学し、実践や教育に活かしていくことを目的としています。暗黙知を形式知に、個人知を組織知に、そして社会知にしてまいります。
教育
プロデュースシンキングを通じて、企業向け・自治体向け・学校向けの学習機会の創出、研修プログラムの導入と様々な領域やテーマに対するプロデューサー育成プログラムの共同開発などを展開。
座学のみならず実学になるようケーススタディやグループディスカッションを通じた学習機会の創出や、新規事業を企画立案するプロセスを提供するプログラム、リスキリングやOSのアップデートといったファンダメンタルな内容から応用まで研修実施してまいります。
研修を通じてプロデューサーになれるといった表層的な資格制度のような型に当てはめるようなものではなく、研修後に実践を通して、経験を積み重ねていくことを前提とし、それを下支えできる素養を身につけることを教育の目的としています。
今後、個人を対象にした学習機会も展開予定です。
コミュニティ
プロデュースシンキングを実践するコミュニティを形成してまいります。
個人が向き合うプロジェクトの相談や共創の機会創出、相互補完・協力関係の構築などを通じ、生きたプロジェクトに対してどのように向き合い、成果に導いていけるか、コミュニティがサポートしていきます。
本コミュニティは、プロデューサーという人とプロジェクトが有機的に、横断的に交流・共創する場を目指しています。また、プロデュースシンキングを実践していく上で、起点となるビジョン確立に向けて重要であるキャリアデザインの側面のサポートもしてまいります。
最終的にはエージェントのようにプロジェクトとプロデューサーをマッチングする役割もこのコミュニティで担っていけると考えております。
啓発
実践、研究、教育を通じて、PRODUCE THINKING LABに蓄積された知見や経験を記事・イベントを通じて、発信をしていきます。
プロデューサーの認識・認知を画一的なものにしていくことが目的ではなく、多様なプロデュースの事例において、いかに変容的な部分と普遍的な部分が重なって事業開発のプロデュースが推進できるのかを認識していただきたいと考えております。